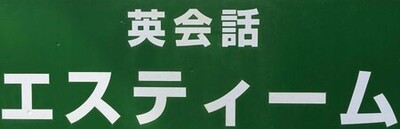「日本語しか話せません」──金沢の飲食店が示す、オーバーツーリズムと行政の盲点

先日、金沢市内を歩いていると、ある飲食店のドアにこんな張り紙が貼られていました。
“We cannot speak English, so we’re afraid we can only accept Japanese speakers in order to provide good service.”
「英語が話せないため、サービスの質を保つためにも日本語を話せる方のみのご案内とさせていただきます。」
とても正直で誠実な表現です。お客様に不便をかけたくないという思いから、このような案内を出されたのでしょう。しかし、この張り紙は、いま金沢が直面しているインバウンド観光とオーバーツーリズムのひずみを象徴しているようにも感じました。
まず冷静になってこのオーナーのとった方針の是非について考察してみましょう。
“We cannot speak English, so we’re afraid we can only accept Japanese speakers in order to provide good service.”
「英語が話せないため、サービスの質を保つためにも日本語を話せる方のみのご案内とさせていただきます。」
とても正直で誠実な表現です。お客様に不便をかけたくないという思いから、このような案内を出されたのでしょう。しかし、この張り紙は、いま金沢が直面しているインバウンド観光とオーバーツーリズムのひずみを象徴しているようにも感じました。
まず冷静になってこのオーナーのとった方針の是非について考察してみましょう。
この方針のメリット
この方針のメリット
正直で誠実な対応
自分たちの言語力の限界をあらかじめ伝えることで、誤解やトラブルを避けることができます。
サービス品質の維持
十分な意思疎通ができないことでお客様に不便をかけるよりも、日本語でしっかり対応できる方に限定することで、満足度の高いサービスを提供しようという姿勢が見られます。
スタッフの安心感
スタッフが慣れた言語で接客できることで、余計なストレスを減らし、スムーズな運営が可能になります。
安全性と効率の確保
食物アレルギーや調理方法に関するやりとりなど、誤解が許されない場面では、言語の壁を避けることが安全につながります。
正直で誠実な対応
自分たちの言語力の限界をあらかじめ伝えることで、誤解やトラブルを避けることができます。
サービス品質の維持
十分な意思疎通ができないことでお客様に不便をかけるよりも、日本語でしっかり対応できる方に限定することで、満足度の高いサービスを提供しようという姿勢が見られます。
スタッフの安心感
スタッフが慣れた言語で接客できることで、余計なストレスを減らし、スムーズな運営が可能になります。
安全性と効率の確保
食物アレルギーや調理方法に関するやりとりなど、誤解が許されない場面では、言語の壁を避けることが安全につながります。
この方針のデメリット
非日本語話者の排除
外国人観光客や日本在住の非日本語話者にとって、このような案内は「歓迎されていない」と感じさせてしまう恐れがあります。
ビジネスチャンスの損失
日本を訪れる観光客は年々増加しており、その中には英語しか話せない人も多数います。そうした潜在的なお客様を逃すことは、収益面でマイナスとなる可能性があります。
イメージダウンのリスク
意図は「丁寧な接客のため」であっても、一部の人からは排他的・閉鎖的に見られてしまう可能性もあります。
柔軟性の欠如
現代では翻訳アプリや多言語メニューの活用など、言語の壁を乗り越える方法も多く存在しています。そうした工夫をすることで、より多くのお客様に対応できる可能性もあるでしょう。
外国人観光客や日本在住の非日本語話者にとって、このような案内は「歓迎されていない」と感じさせてしまう恐れがあります。
ビジネスチャンスの損失
日本を訪れる観光客は年々増加しており、その中には英語しか話せない人も多数います。そうした潜在的なお客様を逃すことは、収益面でマイナスとなる可能性があります。
イメージダウンのリスク
意図は「丁寧な接客のため」であっても、一部の人からは排他的・閉鎖的に見られてしまう可能性もあります。
柔軟性の欠如
現代では翻訳アプリや多言語メニューの活用など、言語の壁を乗り越える方法も多く存在しています。そうした工夫をすることで、より多くのお客様に対応できる可能性もあるでしょう。
増えすぎた観光客と疲弊する地域の現場
コロナ禍明けの現在、金沢には国内外からの観光客が再び戻ってきています。兼六園やひがし茶屋街、近江町市場など、人気の観光スポットはどこも賑わいを取り戻していますが、その一方で、観光業に従事する人々や地域住民にかかる負担は確実に増しています。
とくに言語の壁は、観光地にある飲食店や個人経営の店舗にとって大きなストレスです。「接客したい気持ちはあるけれど、英語が話せない」という現実が、今回のような張り紙に表れています。
とくに言語の壁は、観光地にある飲食店や個人経営の店舗にとって大きなストレスです。「接客したい気持ちはあるけれど、英語が話せない」という現実が、今回のような張り紙に表れています。
観光立国を掲げる行政の想像力不足
このような状況を見ると、行政が推進する「観光立国」と「地方創生」が、どれほど現場と乖離しているかを痛感します。外国人観光客の数ばかりを追い求め、通訳案内士や多言語インフラ整備といった“見える部分”に予算をかけてきた一方で、現場の小さな飲食店や個人店への支援・教育は後回しにされてきたのではないでしょうか。
観光客の「受け入れ体制」を整えるとは、単に案内板を多言語化することではありません。大切なのは、現場に立つ人々が安心して外国人と接することができる力を持つことです。
観光客の「受け入れ体制」を整えるとは、単に案内板を多言語化することではありません。大切なのは、現場に立つ人々が安心して外国人と接することができる力を持つことです。
英会話エスティームの取り組み
英会話エスティームでは、こうした現場の課題を深く理解し、観光対応にも自信をもって臨める実践的な英語指導を行っています。
外国人観光客との自然なやりとりを想定したロールプレイ
日本文化やマナーの英語での説明
接客現場で本当に使えるシンプルで効果的な英語表現の指導
英語が話せないから外国人を断る――そんな悲しい状況を一つでも減らせるよう、地域に根差した語学支援を行っています。
外国人観光客との自然なやりとりを想定したロールプレイ
日本文化やマナーの英語での説明
接客現場で本当に使えるシンプルで効果的な英語表現の指導
英語が話せないから外国人を断る――そんな悲しい状況を一つでも減らせるよう、地域に根差した語学支援を行っています。
最後に:観光は“おもてなし”の延長線
観光業とは、単なる経済活動ではなく、地域の人々の温かさや文化を伝える「おもてなし」の延長線にあるものです。だからこそ、利益だけでなく、現場の声と人材育成にもっと光が当たるべきです。
そして、英語が苦手でも、「伝えたい」という思いと、それを支える学びの場があれば、どんな地域でも心のこもったおもてなしは可能です。
金沢が“本当の意味での国際観光都市”になるために、今こそ、行政・市民・教育が手を取り合うときです。
当校受講生の体験記→
無料体験を申し込む
ホームに戻る
そして、英語が苦手でも、「伝えたい」という思いと、それを支える学びの場があれば、どんな地域でも心のこもったおもてなしは可能です。
金沢が“本当の意味での国際観光都市”になるために、今こそ、行政・市民・教育が手を取り合うときです。
当校受講生の体験記→
無料体験を申し込む
ホームに戻る